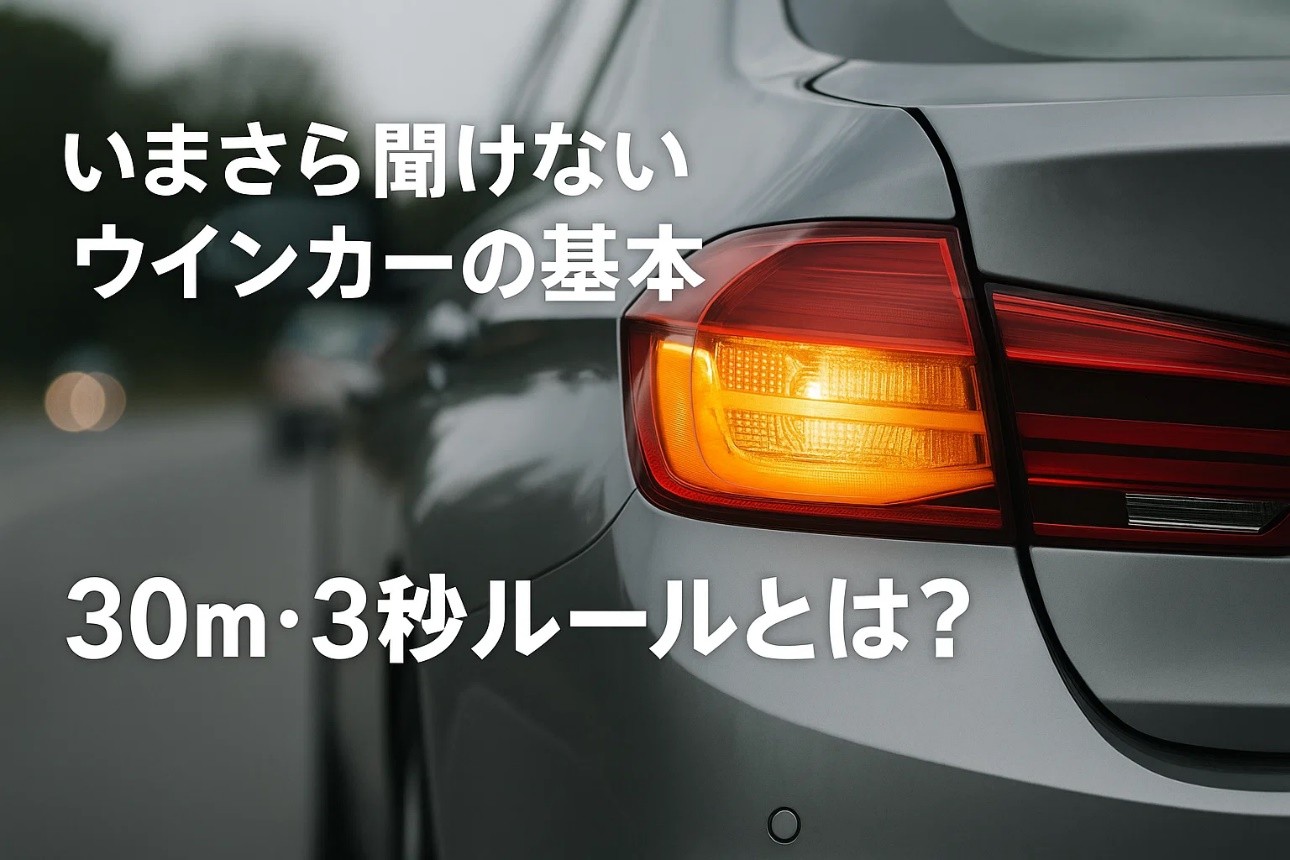2025.11.23
車のビックリマークが点灯したら?色・形別の意味と対処法

最終更新日: 2026.02.12
車を運転していると、ダッシュボードにビックリマークが突然点灯して、慌ててしまうことはありませんか?色や形の違いがわからず、どう対応すればいいか迷う方も多いでしょう。
誰でも突然の警告に焦るのは自然なことです。特に日常的に運転していない方や、久しぶりに車に乗った方なら、戸惑うのも当然ですよね。
安心してください。ビックリマークにはそれぞれ意味があり、色や形ごとに危険度が異なります。正しい知識を持ち、適切に対応すれば事故やトラブルを防ぐことができます。
本記事では、オレンジ・赤・三角マークの違いや点滅時の対応、さらに日常のメンテナンス方法まで分かりやすく解説します。図解やチェックリストも用意しているので、すぐに役立てられますよ。
特に、最近運転に不安を感じ始めた方や、車の警告灯の意味をきちんと理解して安全運転したい方におすすめです。
この記事を読むことで、ビックリマークが点灯しても慌てず落ち着いて対処できるようになります。ぜひ最後までチェックして、今日から安全運転に役立てましょう。
目次
車のビックリマークとは?意味や役割を確認しよう

運転中にビックリマークが点灯すると驚きますが、このサインは車が「何か気になる状態ですよ」と教えてくれるものです。
軽い注意で済む場合もあれば、深刻なトラブルの前触れというケースもあるため、まずは落ち着いて状況を見ましょう。マークの色や点灯の仕方で危険度が変わる仕組みになっており、正しく理解しておくと慌てずに行動できます。特に赤色は緊急性が高いことが多いので、無理に走り続けるのは避けた方がいいですね。
ここから先は、役割や色ごとの違いについて以下で解説していきます。
ビックリマークの役割と意味
このマークは、車の安全装置や各システムが異常の可能性を検知したときに知らせる仕組みです。ブレーキやタイヤ空気圧、横滑り防止装置など、多くの部分と関わっているため、点灯したときは何かしらのサインと受け止めたほうがいいでしょう。
点灯だから危険というわけではありませんが、放置すると状態が悪化することもありますよ。点滅の場合は、異常が進んでいる可能性が高いので注意したいところです。
車によって表示が異なることもあるため、マニュアルを一度確認しておくと安心ですね。
黄色・赤・三角マークの違いと危険度
車のビックリマークは、色や形によって示す意味が大きく変わります。同じマークでも危険度がまったく違うことがあるため、まずは落ち着いて「どの種類が点灯しているのか」を確認することが大切です。
下の表では、代表的な色・形ごとの特徴をまとめました。照らし合わせながら状況を判断してみてください。
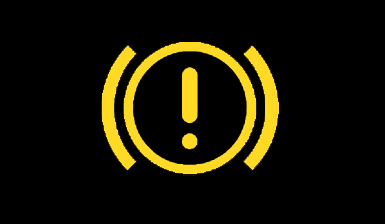



| マークの種類 | 意味・危険度 | 走行の可否 | 推奨される対応 |
| 黄色のビックリマーク | 注意レベル。 軽度の異常や 確認が必要な状態。 | 走行は可能な 場合が多い。 | 早めに原因を確認し、必要なら点検へ。 |
| 赤(オレンジ)のビックリマーク | 重大警告。 緊急性が高い状態。 | 基本的に 走行は避けるべき。 | 安全な場所に停車し、速やかに 原因確認・整備。 |
| 三角+ビックリマーク (黄色のギザギザ) | 複数の異常・広範囲のシステムトラブル。 | 状況によるが放置は危険。 | 点検を急ぎ、整備工場で詳しく診断。 |
車メーカー別|ビックリマーク表示の違い

車のビックリマークは、メーカーによって形状や色、点滅の意味が異なります。慌てず対応するためには、自分の車の仕様を理解することが重要です。
ここでは、スズキ、トヨタ、日産の例を挙げ、それぞれの特徴や点灯時の注意点を解説します。日常点検や緊急時の判断にも役立つ情報なので、ぜひ目を通しておきましょう。
スズキのビックリマーク表示と特徴
スズキ車のビックリマークは、色や点滅パターンで警告の緊急度を示しています。慌てず確認することが大切です。
- オレンジ:軽度の警告。走行は可能ですが、原因を確認しましょう
- 赤・点滅:重大警告。安全な場所で停車し、整備工場に相談
- 図解で色・形を確認すると理解しやすい
- マニュアルで意味を把握しておくと誤判断を防げる
色や点滅の意味を覚えておくことで、点灯時も落ち着いて対応できるでしょう。
トヨタのビックリマーク表示と特徴
トヨタ車では、赤・オレンジ・黄色の三角形やギザギザマークが主に用いられます。表示の意味を理解して、安全に運転を続けましょう。
- 赤:停車が推奨される危険信号
- オレンジ:注意。すぐに整備が必要なわけではない
- 三角・ギザギザ:整備や点検が必要な場合が多い
- 走行中は徐行して、安全な場所で状況確認
マニュアルや車内表示を確認すると、正しい判断がしやすくなります。
日産のビックリマーク表示と特徴
日産車のビックリマークは色・形・点滅パターンがやや複雑ですが、基本を押さえると安心です。
- オレンジ:注意。軽度の警告で簡単なチェックで対応可能
- 赤:危険。安全な場所に停車して整備工場へ
- 点滅:緊急度が高い警告
- 長時間放置せず、早めに対応することが重要
- 色・形・点滅の組み合わせで危険度を判断
点灯したら焦らず、段階的に対応することが事故防止につながります。
ビックリマークを見て慌てやすいケースと正しい対応

車の警告灯が点灯すると、多くの人はつい焦ってしまいます。停車中と走行中では対応が異なるため、状況に応じて安全に行動することが重要です。
軽度の警告なら簡単なチェックで済みますが、重大警告は整備工場で点検しましょう。以下で具体的な対応方法を解説します。
停車中に点灯した場合の安全な対応
停車中に点灯した場合は、まず落ち着いて状況を確認することが大切です。軽度の警告であれば以下をチェックしましょう。
- ドアやボンネットがきちんと閉まっているか
- オイル量や冷却水の量を確認
- タイヤの空気圧や見た目に異常がないか
赤や点滅の場合は無理に走行せず、整備工場に連絡してください。マニュアルや車内表示で内容を確認すると誤判断を防げます。
走行中に点灯した場合の安全な対応
走行中にビックリマークが点灯したら、まず徐行して安全な場所に停車することが重要です。軽度の警告であれば簡単なチェックで状況を把握できますが、赤や点滅は重大なサインです。
- 前方の安全を確保し、段階的に減速する
- 停車後、警告灯の色や形から危険度を判断
- 必要に応じて整備工場に相談
焦らず段階的に対応することで、事故やトラブルを防げますよ。
点滅・消えないビックリマークの対処法

ビックリマークが点滅したり、消えない場合は焦らず原因を確認することが大切です。色や点滅の状態によって危険度が変わるため、安全を最優先に判断しましょう。
自己対応できるケースもありますが、赤や点滅が伴う場合は整備工場に任せるのが安全です。以下で具体的な確認ポイントと対応方法を解説します。
すぐに確認すべきポイント
点滅や消えない場合にまず確認したい項目は次の通りです。
- ドアやボンネットがしっかり閉まっているか
- エンジンオイルや冷却水の量
- タイヤの空気圧や異常の有無
- 点灯・点滅の色と形から危険度を判断
これらをチェックするだけでも、走行のリスクを減らすことができますね。安全第一で確認しましょう。
自分で消せる場合と整備工場に任せる場合
| 状態 | 対応方法 |
| 軽度警告(オレンジなど) | エンジン再始動やリセットで消えることがある |
| 赤色や点滅を伴う警告 | 整備工場で点検が必要 |
軽度の警告灯であれば、まず車のマニュアルを確認し、再始動やリセットで消えるかをチェックしてください。一方、赤や点滅の警告灯は、走行を続けると事故や故障のリスクが高まるため、安全な場所に停車し、整備工場での点検を行いましょう。日常点検を習慣化することで、こうした警告灯の発生を減らすことができます。
ビックリマークを防ぐための日常メンテナンス
ビックリマークの点灯を防ぐには、日常的な車両の点検と整備が重要です。小さな異常も早めに確認することで、警告灯の発生や重大トラブルを未然に防げます。以下のポイントを習慣化すると安心です。
- オイル量のチェックと定期交換
- タイヤの空気圧確認
- ライトやウインカーなど灯火類の点検
- 長距離運転前の簡単チェック(ブレーキ、ドア、ボンネットの確認)
- 車両マニュアルで警告灯の意味を理解
毎日の運転前や週に一度など、決まったタイミングで確認することで、ビックリマークの点灯リスクを減らすことができます。安全運転のための基本として、習慣化しておきましょう。
安全運転のためのチェックリスト
ビックリマークが点灯したとき、慌てず安全に対応することが大切です。日常点検や運転中の確認を習慣化するだけで、トラブルを未然に防げます。
ここからは、運転前・運転中・点検後に確認すべき項目をまとめたチェックリストをご紹介します。毎回チェックすることで、安心して運転できるようになりますよ。
| 時期 | 項目 | 対応 | チェック |
| 運転前 | ビックリマークの色・形 | 点灯していないか確認 | ☐ |
| 運転前 | 点灯・点滅の違い | 点滅か点灯かを確認 | ☐ |
| 運転前 | シート・ミラー・ペダル位置 | 正しく調整 | ☐ |
| 運転中 | 軽度警告(オレンジ色など) | マニュアル通り対応 | ☐ |
| 運転中 | 赤や点滅の警告 | 安全な場所で停車し整備工場で確認 | ☐ |
| 運転中 | メーカー別仕様の把握 | 車内表示やマニュアルで確認 | ☐ |
| 点検後 | 定期点検・整備 | オイル交換・タイヤ空気圧・灯火類を確認 | ☐ |
まとめ|ビックリマークを見たら焦らず対応しよう
ビックリマークを見ても焦らずに対応することが大切です。色や形、点滅状態の意味を理解していれば、緊急時でも慌てず安全な行動がとれるはずです。日々の点検やチェックリストを習慣にしておくことで、警告灯が点灯したときにすぐ判断できます。
軽度の警告はマニュアル通りの確認で十分ですが、赤や点滅の場合は安全な場所に停車して整備工場に相談しましょう。
こうした日常の意識が、事故や故障を防ぎ、車も自分も守ることにつながります。どうしても不安な場合は、迷わずすぐに業者に相談するようにしてください。安全第一の判断が、最も大切ですよ。
CAM-CARではほかにも車に関する豆知識や車中泊の情報を発信していますので是非見てみてください。